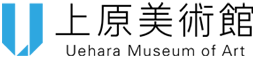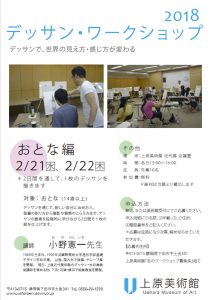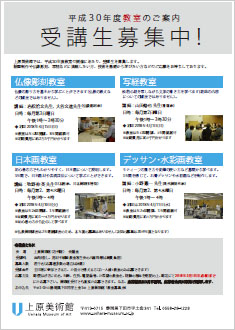*終了しました。
デッサンで、世界の見え方・感じ方が変わる
おとな編
2/21(水)、2/22(木)
※2日間を通して、1枚のデッサンを描きます。
対象:おとな(14歳以上)
デッサンを通じて、新しい自分に出会おう。鉛筆の削り方から陰影や質感のとらえ方まで、デッサンの要素を段階的に学びながら2日間で一枚の絵を仕上げます。
講師:小野憲一先生
1969年生まれ、1993年武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒業。以後、国内外で個展、グループ展を開催。
現在、上原美術館のデッサン・水彩画教室講師を務める他、下田・河津・横浜で絵画教室を開催。
場 所:上原美術館 近代館 会議室
時 間:各日13:00~16:00
定 員:先着10名
参加費:無料 ※画材は当館より貸出します。
申込方法
郵送、または美術館受付にてご応募ください。
申込用紙に
- お名前
- 年齢
- ご住所
- 電話番号
をご記入ください。
※応募は定員になり次第、締め切らせていただきます。
応募先住所
〒413-0715 静岡県下田市宇土金341
上原美術館「冬のワークショップ募集係」宛て