

【近代館】であう、はじまる—画家たちの初期作品
【仏教館】伊豆 民間仏めぐり
| 開催期間: | 2025年4月26日(土)~9月23日(火・祝) |
| 開館時間: | 9:30~16:30(入館は16:00まで) |
| 休館日 : | 展覧会会期中は無休 |
| 入館料 : | 大人1,000円/学生500円/高校生以下無料 ※仏教館・近代館の共通券です ※団体10名以上10%割引 ※障がい者手帳をお持ちの方は半額 |
| 会場 : | 上原美術館 近代館・仏教館 |
【仏教館】伊豆 民間仏めぐり
六世紀に日本に伝来した仏教は、都に仏教文化の大輪の花を咲かせ、やがて各地に伝播しました。古代中世の造像を担ったのは、主に皇族や貴族、地方豪族、武士たちで、この時代、仏教美術の名品が数多く生み出されました。
室町後期から戦国時代になると、仏教が地方の民衆の間にも定着します。やがて江戸時代に入ると、全国津々浦々で民衆が仏像造像を発願し、時には様々な立場や階層の人々が自ら造像するようになりました。こうして生まれた仏像の数は、前代を圧倒します。量で見る限り、江戸時代は仏像造像の黄金時代なのです。
江戸時代の伊豆の人々は、江戸に住む仏師たちに造像を依頼したり、彼らが制作した仏像を購入して寺院やお堂に迎えることが多かったようです。しかしその一方で、各地の寺院の片隅に目を凝らし、地域のお堂を訪ねると、伊豆に生きた作者による仏像も伝えられています。これらの像は職業仏師が作る像と比較すると、素朴な造形の像が多いのですが、不思議な魅力を宿しています。
本展では、伊豆で生まれた、造形的には拙いかもしれませんが、愛らしく、愉快で親しみやすい魅力的な仏像を、伊豆半島の全域から集めて展示いたします。
展覧会紹介動画

【近代館】であう、はじまる—画家たちの初期作品
今では巨匠と呼ばれる画家たちにも、そのはじまりがあります。若く名もなき画家はさまざまな人や芸術と出あい、心を揺さぶられ、そして自らの表現の道を歩みはじめます。本展では画家たちの若き感性があふれる初期作品をご紹介し、その芸術の魅力と本質に迫ります。
《科学と慈愛》はピカソ15歳のときの作品です。幼少の頃より美術教師の父に絵の手ほどきを受けたピカソは、官展のために大作の準備を重ねます。その最終準備作がこの油彩画です。ピカソはこの絵を縦2メートルの大作に仕上げ、マラガの展覧会で金賞を受賞。そしてピカソの画家としての人生がはじまります。
《アニエール、洗濯船》はシニャック18歳の作品。自身の作品帖には最初の番号が振られています。シニャックは16歳の頃、モネに憧れて画家を志しました。セーヌ川の輝くみなもは、モネを思わせる筆触分割で描かれており、理論的な点描主義に至っていない、若き画家の瑞々しい感性に溢れています。
そのほか、駆け出しのゴッホが憧れのミレーの小さな版画を懸命に模写した《鎌で刈る人(ミレーによる)》、株式仲買人の仕事をしていたゴーギャンが日曜画家として描いた最初期の油彩画《森の中、サン=クルー》、自らの芸術を模索する若き梅原龍三郎が師ルノワールに見せ助言を受けた《モレー風景》、西洋美術研究のため大学院を中退してスペインに渡った須田国太郎がその地の風景を描いた《山の斜面》など、画家たちの初期作品をご紹介します。
上原コレクションには、画家たちのはじまりの作品が多くあります。そこには画家の人間性を見つめるコレクターの小さくやさしい「まなざし」にあふれています。画家たちの初期作品を通じて、上原コレクションの魅力をどうぞお楽しみください。
展覧会紹介動画
作品リストPDF
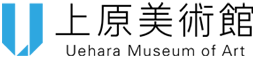
 展覧会チラシ(PDF)
展覧会チラシ(PDF)