
仏像は、仏教の聖なる尊像であり、仏教徒の信仰対象、心のよりどころです。古代中世、仏像を制作した仏師たちの多くは、宗教者でもあり、その優れた技術に、自らの信仰を込め、丹精込めて仏像を作りました。こうして作られた仏像は、美しく、現代では彫刻作品としても高い評価を受けています。またこれらの仏像は、鎌倉時代なら七百年から八百年、平安時代なら九百年、あるいは千年を超える時を越えて、現代に伝えられてきました。古い仏像は歴史を考える上で、貴重な文化財でもあります。
上原美術館は開館以来、古く優れた仏教美術の収集に努め、多くの仏像を収蔵してきました。当館ではこの度、納入願文により、鎌倉時代の文永七(1270)年に制作されたことが分かる、阿弥陀如来像を収蔵しました。本展ではこの像を初公開するとともに、当館が所蔵する全ての仏像を展示いたします。
古代中世の仏像が、彫刻作品として高い評価を受ける一方、各地の寺院やお堂を訪ねると、それ以外の数多くの仏像に出会います。その多くは、江戸時代に造られた仏像で、古くても四百年前、ほとんどが二百年そこそこの若い仏像たちです。江戸時代の仏像は新しいだけでなく、たいていはとても小さく、造形は拙く、見劣りがします。しかし、これらの像に向き合うと、それらのお像に込められた祈りと、素朴で愛らしい姿に触れることができます。上原美術館では開館以来、四十年に渡り、伊豆の仏教美術の調査を継続してきました。調査によって見出された仏像の大多数は、江戸時代のものですが、これまでは、江戸時代の仏像を展示し、紹介する機会はほとんどありませんでした。本展では当館が出会った、素朴ながら愛らしく、愉快な仏像十数点を厳選して展示します。当館所蔵の仏像と、伊豆に伝えられた愉快な江戸時代の仏像の競演を是非ご覧ください。
展覧会紹介動画
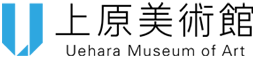
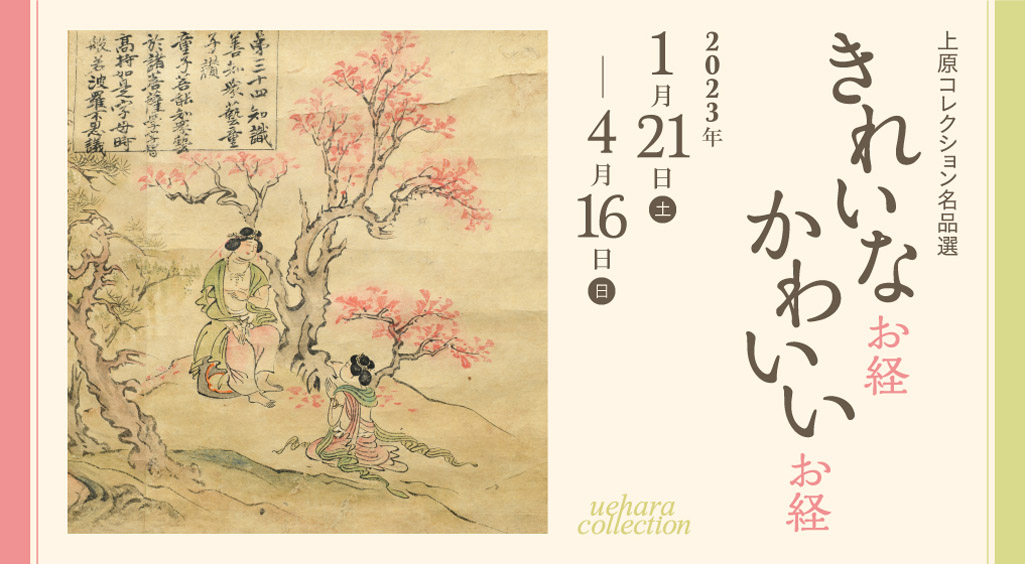
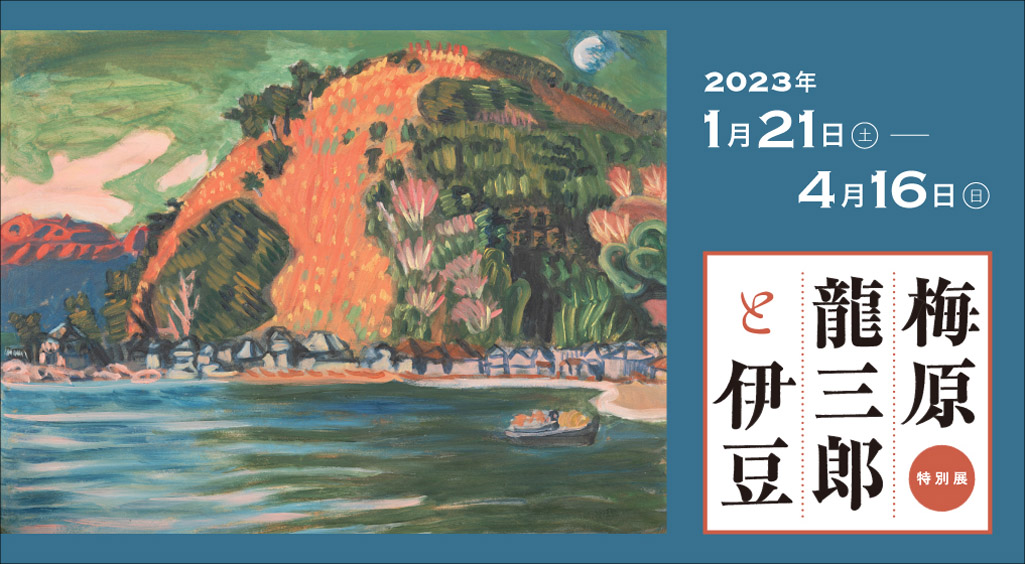



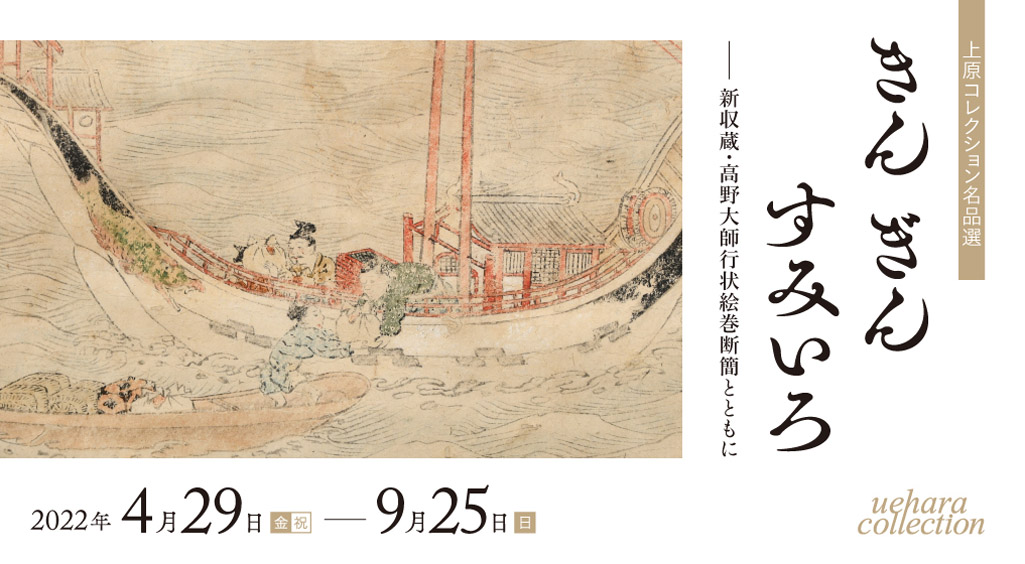


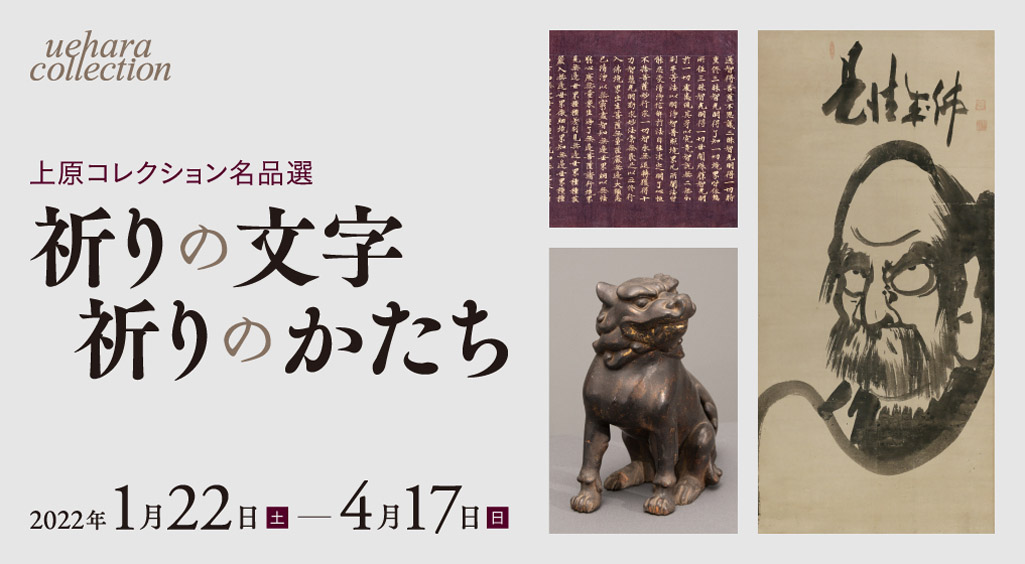
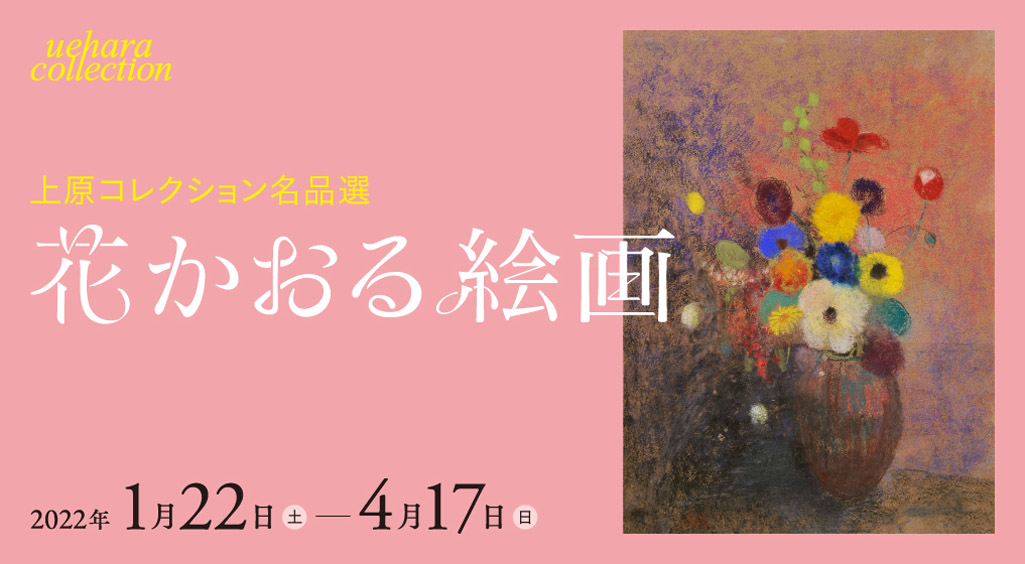

 展覧会チラシ(PDF)
展覧会チラシ(PDF)