上原美術館では、『上原美術館でワークショップ』を開催します。
この冬、おやこでアート体験をしてみませんか?
参加費無料
上原美術館アトリエにて開催
いろの世界をのぞいてみよう!
講師:小野憲一先生 現代美術作家/当館デッサン・水彩画教室講師
日時:2026年2月1日(日) 13:30~15:10(最終15:30)
対象:5歳以上のこどもと保護者
しめきり:1月22日(木)
定員:8組
おやこできもちをえがいてみよう!
講師:牧野伸英先生 日本画家/当館日本画教室講師
日時:2026年2月23日(月・祝) 13:30~15:00(最終15:30)
対象:5歲以上のこどもと保護者
しめきり:2月12日(木)
定員:8組
応募方法
【Googleフォーム】
①QRコードを読み込み、必要事項をフォームに記入し、お申込みください。
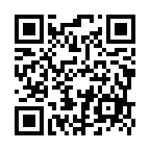
【はがき】
①参加者全員の氏名、②年齢、③住所、④メールアドレス、⑤電話番号、
⑥参加希望のワークショップを記入し、上原美術館「イベント」係宛にお申し込みください。
※定員以上のお申し込みがあった場合は、抽選といたします。
※抽選結果につきましては、メールまたはお電話にて応募締切から2日以内にご連絡申し上げます。
その他、ご不明な点がございましたら上原美術館までご連絡ください。
Tel. 0558-28-1228