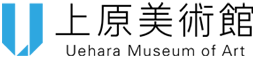「ものとは何か」。それは古来より哲学者が向き合ってきた問いのひとつです。「もの」という言葉は、そこにあって掴むことのできる対象をあらわす一方で、それ以上の「何か」を含んでいます。画家たちは静物画を描くとき、ある「もの」を描きながら、その後ろに広がる大きな存在を見つめています。
セザンヌ《ウルビノ壺のある静物》は、布の上に置かれた果物と西洋トマト、色鮮やかなマヨルカ焼の壺が描かれています。壺は真正面から捉えられ、背景に大きな影を映します。右奥にあるカーテンは、模様が生き生きとした筆致で描かれ、布の上のモティーフと呼応するかのようです。再び果物や壺に目を移すと、それらは空中に浮かび上がるかのように不思議な存在感を放ち始めます。
セザンヌが本作を描いたのは30代前半。先輩の画家ピサロの影響を受けながら、自らの絵画を模索する時期でした。この頃、セザンヌとピサロはともに絵を描き、近くに住む医師ポール・ガシェの家を度々訪ねました。ガシェはパリのカフェで印象派の画家たちと芸術論を交わし、自らも絵や版画を制作するパトロンでした。自宅にはアトリエもあり、友人の画家を招きますが、そのガシェの家で描かれたのが本作です。セザンヌは本作と全く同じ構図の静物を、別の角度からも立体的に描いています。セザンヌはこのとき平面や立体を行き来することで、「もののありか」そのものに問いを投げかけています。そうしたセザンヌのまなざしは、間もなくリンゴが転がるような独特の静物画を生み出していきます。
本展では画家たちが描く「もの」へのまなざしに注目することで、「静物画のふしぎ」に迫ります。セザンヌの影響のもと新たな表現を模索する若き安井曽太郎による《静物》、光を浴びる果物と平面的な装飾模様が対照的なマティス《果物皿の傍に立つオダリスク》、生命の儚さをあらわすモティーフを現代的に捉えたドラン《静物》、印象派の色彩に伝統美を融合させたルノワール晩年の《果物の静物》など、画家たちによる「もの」へのまなざしをご紹介します。画家たちが描き出す「静物画のふしぎ」をお楽しみください。
展覧会紹介動画