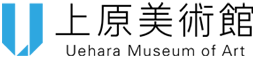「梅の花 香をかぐはしみ 遠けども 心もしのに 君をしぞ思ふ」(市川王、天平宝字2[758]年、万葉集)。これは今から1200年以上前の宴で、梅の香りに託して敬愛の心が詠まれた歌です。日本の芸術では古来より花の香りにさまざまな思いが重ねられてきました。その香りを想像すると、それまでには感じられなかった世界が目の前にあらわれます。絵画もまた、描かれた花の香りをイメージすると、そこには豊かな空間が広がっています。
ルドンが描き出す《花瓶の花》にはアネモネをはじめ色とりどりの花が咲き乱れています。ルドンは自らが描く花を「再現と想起という二つの岸の合流点にやってきた花ばな」と述べました。現実の花が夢幻の世界と合流するように混じり合うその香りは、パステルの不思議な色彩と相まって見るものを幻想的な世界へと導きます。当時の批評家はルドンの花の絵画について次のように述べています。「花がパステルになったのか、パステルが花に変容したのかだれもしらない。(中略)それは控え目だが変わることのない匂いがする。それは妖精だろうか。女神だろうか。いや、それ自身である」。
ピサロ《エラニーの牧場》では、牛が草をはむ田園風景の中に林檎の花が咲き誇っています。明るい色彩であらわされた花々は甘い香りを漂わせて、北フランスの湿潤な大気の中を吹き抜ける爽やかな風を感じさせます。安井曽太郎《桜と鉢形城址》は終戦間近の1945年春に描かれた作品です。疎開先である埼玉県寄居町に桜が咲き誇る田園風景には、穏やかな春の香りが広がります。
本展ではモネ、ルノワール、マティス、梅原龍三郎など上原コレクションから花の香り漂う絵画をご紹介します。美しい花々に包まれてゆったりとしたひとときをお過ごしいただけましたら幸いです。
展覧会紹介動画